はじめに
トーンウッドに関する議論: ギターコミュニティでは、ギターのボディ、ネック、または指板に使用される木材である「トーンウッド」がサウンドに与える影響について、激しい議論が交わされてきました。アコースティックギターでは、木材の選択が楽器の音色と共鳴を強く形作ることが確立されています。しかし、共鳴するサウンドボックスではなく、磁気ピックアップとアンプに依存するソリッドボディのエレキギターの場合、木材の効果はそれほど明確ではなく、しばしば疑問視されます。メーカーは長い間、エキゾチックまたは重い木材がエレクトリックギターのサステインと音色を向上させると宣伝してきましたが、懐疑論者はピックアップとエレクトロニクスがサウンドを支配すると主張しています。
アコースティック vs. エレクトリック: アコースティックとエレクトリックのコンテキストを区別することが重要です。アコースティックギターでは、木製のサウンドボードとボディが直接サウンドを生成し、色付けします。木材の剛性、密度、および減衰が、振動する空気、ひいては音色を形作ります。対照的に、ソリッドボディのエレキギターでは、弦の振動(磁気ピックアップによって感知される)が主要なサウンドソースであり、ソリッドウッドボディの役割は主に構造的です(弦とピックアップを保持するため)。ソリッドボディは元々、アコースティックフィードバックと不要なボディの共鳴を最小限に抑えるために導入されました。理想的には、ソリッドボディはアコースティックのサウンドボックスのように聞こえないように、十分に剛性が高く、質量が大きい必要があります。その結果、多くの人は、ソリッドエレキギターの木材の選択が音色に及ぼす影響はごくわずかであると想定しています。それにもかかわらず、これからわかるように、弦と木材の間の微妙な機械的相互作用は、エレクトリックギターの振動の減衰、周波数応答、および演奏感に影響を与える可能性があります。
研究範囲: この記事では、科学的なレンズを通して、ソリッドボディのエレキギターにおけるトーンウッドの効果を検証します。音響学および心理音響学における査読済みの研究に焦点を当て、木材が弦の振動に影響を与える可能性のある物理的メカニズムを調査し、これらの効果の実験的測定をレビューし、実際に人間の耳に聞こえる違いについて議論し、検証済みの調査結果を使用してトーンウッドに関する一般的な神話を暴くか、確認します。重点は、木材の影響が微妙なソリッドボディのエレキギターに置かれています。引用されているすべての証拠は、管理された実験、信号分析、または厳密なモデリングからのものであり、中立的で技術的に根拠のある視点を保証します。

物理的メカニズム:木材が弦の振動にどのように影響を与えるか
弦と構造の結合: ソリッドボディのエレキギターでは、弦はブリッジとネック(ナットまたはフレット経由)で木製構造に結合されています。弦が振動すると、電磁ピックアップで音を生成するだけでなく、ギターのボディとネックに力を加えます。木材と構造が無限に剛性でない場合、わずかに振動することで応答します。これにより、フィードバックループが導入されます。弦のエネルギーの一部は、弦の動きにとどまる代わりに、木材に伝達されます(ボディ/ネックの振動を励起します)。物理学的には、弦は振動システム(ギターのボディ/ネック)に結合されており、それらが一緒に機械的に結合されたシステムを形成します。この結合の程度は、弦の取り付けポイントでの機械的インピーダンスまたはコンダクタンスに依存します。基本的に、構造が弦によってどれだけ簡単に振動させられるかです。剛性が高く、質量が大きいサポートはコンダクタンスが低く(動きに抵抗する)、柔軟または共鳴するサポートはコンダクタンスが高く(より多くの動きを可能にする)なります。
-
剛性 vs. 柔軟性: ギターのボディとネックが無限に剛性が高く、質量が大きい場合、弦は不動の物体に固定されているかのように動作し、エネルギーを保存してより長く振動します。実際には、すべての木材にある程度の弾性と有限の質量があります。より軽量またはより柔軟な木材は、弦に応じてより多く振動し、弦のエネルギーのシンクとして機能し、弦の振動がより速く減衰します。より密度が高く、剛性の高い木材は、より剛性の高い終端を提供するため、弦から伝達されるエネルギーが少なくなり、サステインが長くなります。これが、エレクトリックギターの伝承で、より重く、硬い木材がより良いサステインと関連付けられることが多い理由です。科学的研究は原則を確認しています。たとえば、より柔らかい木材ではなくより剛性の高い木材(アッシュ)でギターのボディを作ると、構造の共振周波数が上がり、弦からのエネルギー損失が減少する可能性があります。
-
木材の減衰: 剛性と質量に加えて、木材は内部減衰特性を持っています。振動エネルギーを熱として散逸させる傾向です。異なる種は異なります。一部の広葉樹(例:メープル、アッシュ)は内部減衰が低い傾向があり(より多く鳴る)、他の広葉樹(例:マホガニー、バスウッド)は減衰が高く、振動をより速く「吸収」する可能性があります。エレクトリックギターでは、減衰の高い木材は弦のエネルギーをより速く吸収し、サステインを短くする可能性があります。一方、減衰の低い木材は、エネルギーをより効率的にやり取りしたり、より長く保存したりします。最近のアッシュとウォールナットのボディを直接比較した実験では、ウォールナット(剛性が低く、減衰が高い)ギターは、アッシュボディと比較して、楽器の最低共振モードで測定可能な振動減衰が高く、サステインが短いことがわかりました。特に、この効果は木材の振動応答と実際のピックアップ出力信号の両方で観察され、木材の減衰が弦の可聴サステインに影響を与えていることを示しています。
共振とデッドスポット: 木材のボディとネックは、多くの共振モード(振動しやすい自然周波数)を持つ複雑なオブジェクトを形成します。弦の周波数(またはその倍音の1つ)が構造共振と一致する場合、エネルギー伝達が増幅されます。弦はその周波数でより容易にエネルギーを木材にダンプします。これにより、フレットボード全体の減衰時間が不均一になる可能性があり、悪名高いデッドスポットの現象も含まれます。「デッドスポット」とは、弦のエネルギーがネックまたはボディの共振振動に吸い込まれるため、隣接する音符よりも著しく速く消える音符(通常、特定のフレットの1つの弦上)です。
-
ネックのコンダクタンス: FleischerとZwicker(1999年)による先駆的な測定により、デッドスポットの周波数において、ギターネックの機械的コンダクタンス(モビリティ)が局所的に非常に高いことが示されました。これは、ネックが容易に振動し、弦のエネルギーを吸収することを意味します。彼らは、実際のギターの音の減衰時間を測定し、ネックのその場での振動測定と相関させました。その結果、明確な逆相関が得られました。ネックが強く振動する(コンダクタンスが高い)場所では、弦の減衰時間(サスティーン)が短く(デッドスポット)、その逆もまた然りでした。図1は、この効果を示しています。サンプルエレキギターでは、3フレット(デッドスポット)でフレットされたG弦は、6フレット(通常の「ライブ」ノート)よりもほぼ2倍速く減衰し、デッドスポット周波数でのネックの顕著な共鳴に対応しています。このことは、木材の特性と構造(特にネックの木材、取り付け方法、ヘッドストックの設計)が、周波数に依存するサスティーンの変動を生み出す可能性があることを強調しています。多くのベースおよびギター奏者は、楽器上の特定のデッドノートに精通しています。科学的には、これらは楽器の材料と構造がそれらのノートにどのように応答して振動するかに結びついています。
全体と部分 – ボディ、ネック、指板: 一般的なソリッドボディギターでは、複数の木材部品が使用されます。ネック(多くはメイプルまたはマホガニー)、指板(ローズウッド、メイプルなど)、ボディ(アルダー、アッシュ、マホガニーなど)です。ネック+指板のアセンブリは、ボディ単体よりも弦の振動に大きな影響を与えることがよくあります。なぜなら、ネックは比較的細長く(頑丈なボディよりも剛性が低い)、弦の張力でたわむ可能性があるからです。実際、多くの周波数において、弦と構造の結合は主にボディではなくネックで発生することが研究で示されています。これは、ネックの木材と構造(例えば、ボルトオン対セットネック)がサスティーンとデッドスポットに強く影響することを意味します。プレイヤーは、例えば、メイプル対ローズウッドの指板の違いを聞き分け、一方を明るさや歯切れの良さの要因とすることがよくあります。物理学的な観点から見ると、指板は振動するネックシステムの一部です。その密度と剛性の違いは、ネックの共振周波数や減衰を変化させる可能性があります。指板の木材による知覚される違いが調査されており、Patéらの実験では、指板の素材のみを交換し、ギターの周波数特性とサスティーンにわずかではあるが測定可能な違いが見られ、テスト条件下では訓練されたリスナーにも知覚可能でした。したがって、ボディの寄与がゼロではない一方で、ネック/指板の木材は、弦の振動挙動に同等またはそれ以上の影響を与える可能性があります。
振動モードと周波数特性: 木材の特性は、ギターのモード周波数、つまりギターの構造が好んで振動する特定の音色を決定します。一般的に、剛性が高く、密度の高い木材は、柔らかく、軽い木材と比較して、より高い共振周波数(ギターのモードはより高い音程で発生)を生み出します。例えば、Materials誌の2021年の研究では、アッシュとウォールナットのボディで作られた同一のギターを比較し、アッシュ(弾性率が高い)が楽器全体のより高いモード周波数につながることを発見しました(例えば、最も低いボディ/ネックの共振モードは、アッシュでは約118 Hz、ウォールナットでは約108 Hzでした)。より高い共振は、楽器が低いギターの音と強く相互作用する可能性が低いことを意味し、これは有益です。実際、同じ研究では、アッシュギターは、重要な低周波モードでの全体的な減衰が減少し、それに応じて低い音とそのハーモニクスのサスティーンが長くなることがわかりました。逆に、ウォールナットの楽器は、より柔軟なボディを持ち、これらの周波数でより多くの減衰を示し、低い音でのより柔らかいアタックまたはより速い減衰につながる可能性があります。
ソリッドボディギターは通常、共振を最も音楽的に重要な範囲から遠ざけるか、少なくとも抑制して、かなり均一なレスポンスを実現することを目指していることに注意することが重要です。強い共振が望ましいアコースティックギター(音量と音色のために)とは異なり、エレキギターの理想は、弦からエネルギーを奪わない「無限の梁」に近いかもしれません。実際には、完全に剛性のある木材は存在しないため、すべてのエレキギターは、ある程度の共振と減衰を持っています。問題は、その大きさと、これらの効果が聞こえるほど大きいかどうかです。
磁気ピックアップと木材の相互作用: よくある質問は、ピックアップ自体(磁石である)が、木材との関係においてサスティーンや音色に何らかの影響を与えるかどうかです。高強度のピックアップ磁石は、弦にわずかな抵抗力(磁気減衰と呼ばれることもある)を与える可能性がありますが、実験では、この効果は通常の設定では無視できることが示されています。ある厳密な研究では、2つの減衰メカニズム(弦の固有損失とギターとの結合による損失)を分離し、電磁ピックアップが弦の振動に追加の減衰を与えることはないことを明確に示しました。言い換えれば、ピックアップは弦を感知するだけで、その動きを著しく妨げることはありません。さらに、ピックアップは主に弦の振動の特定の偏光に敏感です。水平方向の動きよりも、垂直方向の動き(面外、つまりギターのボディに垂直)をはるかに「聞きます」。これは、木材の振動が弦をわずかに異なるパターンで動かす場合、ピックアップは振幅またはサスティーンの変化を記録する可能性があることを意味します。ただし、木材またはピックアップ自体の直接的な動き(可聴の場合、マイクロフォニックと呼ばれることが多い)は最小限です。ある研究では、ソリッドボディのピックアップの振動は弦信号の1%未満であり、問題にならないほど小さいことがわかりました。したがって、木材はエレキギターのサウンドに間接的に影響を与えます。アコースティックギターのように独自の音響サウンドを追加するのではなく、弦の振動の減衰とスペクトルに影響を与えることによって影響を与えます。

実験的証拠: エレキギターにおけるトーンウッド効果の測定
サスティーンと減衰時間の測定: 多くの管理された実験で、異なる木材が振動する弦の減衰率(つまり、サスティーン)をどのように変化させるかを定量化しています。J. Acoust. Soc. Am.誌のPaté、Le Carrou、Fabre(2014)による画期的な研究は、エレキギターのサスティーンに関する理論的および実験的枠組みを提供しました。彼らは、はじかれた弦の2つの主要な減衰源を特定しました。(1)弦の内部損失(空気抵抗、金属内部の摩擦など)、および(2)ギターのネック/ボディへの機械的結合。孤立した弦とギターに取り付けられた弦を測定することにより、弦が楽器上でどれだけ速く減衰するかを定量化しました。重要なことに、弦自体の減衰とギターのネックでの機械的コンダクタンスを知っていれば、任意の音の減衰時間(T30)を予測できました。予測は測定されたサスティーン時間とよく一致し、ネックでの木材による減衰が、フレットボード全体のサスティーンの変動の背後にある支配的な要因であることを検証しました。さらに、彼らは、エレキギターのピックアップがこれらの減衰の変動を忠実に捉えることを確認しました。ピックアップの出力は、センサーで測定されたのと同じ不均一な減衰時間(デッドスポットなど)を示し、電子機器を追加してもサスティーンの違いを隠したり、変更したりしませんでした。
Rayら(2021)による別の研究では、ボディ材の効果を分離するために、アッシュボディのギターとウォールナットボディのギターという2つの同一のギターを直接比較しました。加速度計、インパルス励起、および注意深いプラックを使用して、彼らは開放弦のモード減衰とサスティーンを測定しました。アッシュボディのギターは、より剛性が高く、重いため、最も低いモードでより低い減衰(tan δ)を示し(例えば、最初のモードではウォールナットの0.121に対して0.093)、それに応じて低いE2、A2、D3弦のハーモニクスの減衰時間が長くなりました。これらの違いは統計的に有意でした。例えば、ウォールナットボディは、最初のモードで約30%高い減衰を引き起こし、高周波モードではほぼ2倍の減衰(〜0.046対0.026)を引き起こしました。これは、高調波に対応します。注目すべきことに、これらの測定値はピックアップ信号にも反映されていました。実際のエレキギターの出力を比較すると、ウォールナットギターの低い音は、アッシュギターよりも速く減衰し、ピーク振幅が低くなりました。これは、増幅されたサウンドでも、木材によるサスティーンの違いが現れる可能性があることを確認しています。ただし、その大きさに注意することも重要です。Rayらは、ほとんどの弦の基本周波数に有意な減衰時間の違いは見られなかったことを発見しました。主な違いは、低い弦の特定の倍音(高調波)と、高い弦の特定のモードで発生しました。言い換えれば、音の全体的なサスティーン(基本周波数によって支配される)は、木材間で非常に類似している可能性がありますが、サウンドの高周波成分では違いが生じます。この微妙な結果は、エレキギターにおけるトーンウッドの効果は現実的ではあるが、微妙であり、特定の周波数成分に影響を与え、他の周波数成分には影響を与えないことを示唆しています。
周波数スペクトルと音色: サスティーンに加えて、研究者は、異なる木材がエレキギターのサウンドのスペクトルコンテンツ(音色)を変化させるかどうかを調査してきました。木材は特定の周波数を優先または減衰させる可能性があるため、弦の振動におけるハーモニクスのバランスを変化させる可能性があります。Jasińskiら(2021)は、さまざまなボディ材を備えた特別に構築されたテストギターで一連の音を録音し、出力スペクトルを分析することにより、この問題に取り組みました。彼らは、木材の種類間でスペクトルエンベロープ(周波数全体のエネルギーの分布)に測定可能な違いがあるだけでなく、全体的な信号レベルにも違いがあることを発見しました。例えば、ある木材はわずかに強い基本周波数を生成するかもしれませんが、高い倍音の減衰が速く、別の木材は高周波ハーモニクスを少し長く鳴らすかもしれません。これらの違いを定量化し、既知の心理音響閾値と比較しました。有望な結果は、スペクトルの違いの大きさが、文献で報告されている音色の変化に対する最小可聴差(JND)を超えていたことでした。平たく言うと、木材の交換によって引き起こされる音色の変化は、平均的な耳が検出できる最小の違いよりも大きく、理想的な条件下では可聴である可能性を示唆しています。実際、この研究では非公式なリスニングテストを実施し、平均的なリスナーが、制御された設定で異なるトーンウッドからのサウンドを確実に区別できると報告しました。これは、たとえその指紋が微妙であっても、木材がエレキギターの音色に知覚可能な「指紋」を与えることができるという証拠を提供します。
一方、他の研究では、特定の音色メトリックへの影響は最小限であることがわかりました。Puszynskiらによる2015年の実験では、さまざまな木材で作られたギターから録音されたエレキギターの音の標準的な心理音響パラメータであるシャープネス、ラフネス、特定ラウドネスを測定しました。彼らは、ボディ材を変更しても、これらの音色記述子に有意な変化は生じなかったと報告しました。木材の種類は、サウンドエンベロープと最大振幅に影響を与えましたが(サスティーンとアタックの違いと一致)、これらのメトリックで定量化されるように、明るさやハーシュネスなどの品質を著しく変化させることはありませんでした。さらに、サウンドが磁気ピックアップまたは外部マイクを介して録音されたかどうかは結果を変えませんでした。これは、ピックアップでキャプチャされたトーンが木材の違いの影響を受けないわけではないことを裏付けていますが、これらの違いは、劇的なスペクトルの再形成ではなく、振幅と減衰にあります。
これらの調査結果をどのように調和させるのでしょうか?木材によるスペクトルの違いは存在するものの、それらは弦の主要なトーンに重ねられた比較的小さな変動であるようです。例えば、ある木材はギターの出力の特定の周波数帯域で1〜3 dBの違いを引き起こす可能性があります。隔離された状態(静かな部屋、単音)では、Jasińskiらが示したように、何を聞くべきかを知っていれば、耳はそのような違いを検出できます。しかし、これらの違いは、「シャープネス」のような広範なメトリックや、重度にマスクされた信号(フルバンドミックスなど)では、針を大きく動かさない可能性があります。要するに、素材の選択はギターの出力のEQを微妙に形作ることができますが、ピックアップの種類やアンプの設定の違いほど、根本的に異なるボイスを作成するほどではありません。
ケーススタディ – 指板材: 特定の焦点の1つは、多くのエレキギターがメイプルとローズウッドの指板オプションを提供しているため、指板(フレットボード)材が音色に影響を与えるかどうかです。Patéら(2015)による管理されたテストでは、指板材(エボニー対ローズウッド)を除いて、あらゆる点で同一のギターを構築し、ギタリストによるリスニング実験を実施しました。この研究では、プレイヤーは違いを識別できましたが、その効果は大きくありませんでした。それは明るさとアタックの微妙な変化として現れました。音響的には、エボニー(密度が高く、硬い)は、ローズウッドよりもわずかに長いサスティーンと明るい初期トランジェントを与えました。これは、硬い木材は弦のエネルギーを反射し、高周波振動をより長く維持するのに対し、柔らかい木材は弦の振動から「エッジ」を少し多く吸収するという一般的なルールと一致しています。興味深いことに、プレイヤーは客観的なスペクトルデータと一致する定性的な用語で違いを説明し、測定可能な物理学と知覚される音色の間の関連性を示しました。このレベルの厳密なテストは、わずかな木材の変化でも、適切な条件下では可聴になる可能性があることを裏付けていますが、ピックアップやアンプのEQと比較して二次的な効果のままです。
測定の概要: まとめると、高精度の測定は以下を確認しています。
-
サスティーン/減衰: 木材の特性(密度、弾性率、減衰)は、弦の減衰時間に測定可能な影響を与えます。剛性が高く、減衰の低い木材は、より長いサスティーンを生み出します。より柔軟で、減衰の高い木材は、特に特定の共振周波数で、より短いサスティーンにつながります。デッドスポットは、これの極端なケースであり、木材/ネックの共振に根ざしています。
-
振幅: 音の最大振幅(または初期アタック)は、木材によって異なる場合があります。これは、エネルギーをすばやく吸収する木材が、ピックアップ信号でわずかに低いピークを生み出すためです。ある研究では、木材の種類が記録された音の最大音圧レベルに大きく影響することがわかりました(アッシュ対アルダーなど)。これは、一部の木材がより「パンチの効いた」アタックを生み出すことを意味します。
-
周波数コンテンツ: ハーモニックコンテンツには微妙な変化があります。例えば、特定の木材は、倍音と比較して基本周波数をわずかに強く鳴らすか、またはその逆にする可能性があります。スペクトルの違いが観察されており、制御されたテストでは聴覚の閾値を超える可能性があります。ただし、それらは、ピックアップやトーンノブを大きく変更するほど、全体的な音色特性を根本的に変更することはありません。心理音響分析では、異なる木材のラフネス/ブライトネスメトリックに大きな変化は見られなかったため、違いは控えめであることが確認されています。
-
一貫性: 多くの実験では、違いが単なる演奏のバリエーションではないことを確認するために、再現性(例えば、プラックマシンまたは一貫したハンマー衝撃)を強調しています。信頼できる研究では、複数の試行後に統計的に有意な結果が報告されており、違い(たとえ小さくても)が現実であり、ランダム性ではなく、材料によるものであるという確信が高まります。
心理音響的視点: 私たちは違いを聞き分けることができるのか?
最終的に、エレキギターにおけるトーンウッドの実用的な重要性は、心理音響学にかかっています。つまり、人間の耳と脳が物理学が測定する違いを知覚できるかどうかです。制御された条件下での可聴性を示唆するリスニングテストについてはすでに触れました。ここでは、木材関連の違いが既知の聴覚閾値および知覚要因とどのように比較されるかをより深く掘り下げます。
最小可聴差(JND): さまざまなサウンド属性のJNDは、可聴性の基準となります。ラウドネス(サウンドレベル)の場合、JNDは中レベルのサウンドで1 dB程度です。それよりも小さい変化は検出が困難です。周波数/音色の場合、より複雑です。スペクトルコンテンツの変化は、少なくともスペクトルの一部で有意である必要があります。金管楽器の音色に関するある研究では、特定のスペクトルエンベロープの変更のJNDが、フォルマント振幅の変化の数パーセント程度であることがわかりました。ギターのコンテキストでは、木材の変更が、例えば、特定のハーモニクスで2〜3 dBの違いにつながる場合、これは閾値を超えており、わずかな音色の違いとして聞こえる可能性があります。一方、その違いが多くの周波数にわたってわずか0.5 dBである場合、気づかれない可能性があります。Jasińskiらの研究では、木材からのスペクトルの違いが、音色の典型的なJNDを超えていることを明確に指摘し、可聴性を示唆しました。彼らはさらに、非専門家のリスナーが偶然よりも高い確率で録音を区別できる非公式なリスニングテストによってこれを裏付けました。
サスティーンの知覚: サスティーンまたは減衰時間の人間の知覚は、違いが大きくない限り、それほど鋭敏ではありません。ある音が1秒で消え、別の音が3秒間鳴り響く場合、プレイヤーは確かに気づくでしょう(これはデッドスポットのシナリオです)。しかし、例えば、減衰時間の5%の変化は微妙であり、多くの場合、音楽のコンテキストまたは演奏スタイルによってマスクされます。木材Aで作られたギターの音が5.0秒のサスティーンを持ち、木材Bが4.5秒のサスティーンを生み出す場合、リスナーが通常の演奏中にその10%の違いを知覚できるかどうかは疑わしいです。ただし、デッドスポット(サスティーンが半分にカットされる)のような極端なケースは絶対に目立ちます。ギタリストは日常的にすぐに「チョークアウト」する特定のフレットを特定します。ミュージシャンはサウンドと同じくらいフィーリングに焦点を当てることが多いことに注意する価値があります。音が速く消えることは、演奏するフィーリングが異なる可能性があり(指へのフィードバックが少ない)、音色のプレイヤーの知覚にバイアスをかける可能性があります。演奏フィーリングが排除されたブラインドテスト(録音を再生)では、わずかなサスティーンの違いを検出することがさらに困難になる可能性があります。
マスキングとコンテキスト: フルバンドミックスまたはヘビーなディストーションでは、わずかなスペクトルまたはサスティーンの違いはマスクされる可能性があります。人間の聴覚システムにはマスキング効果があり、大きな音と複雑な混合音は、1つの楽器のわずかな音色の違いを拾い上げることを困難にします。例えば、木材によって引き起こされる違いは、クリーンで分離されたギターのトーンでは明らかになる可能性がありますが、ドラム、ベース、および飽和したアンプを追加すると、完全に消えてしまいます。心理音響的には、木材の効果は、実験室で測定可能であっても、現実的なシナリオでは可聴性の閾値を下回る可能性があります。これは、プレイヤーの意見が異なる理由を説明しています。ソロまたはスタジオの条件では、マホガニーボディはアルダーよりも暖かい音がすると断言するかもしれませんが、ライブバンドの設定では、その区別はほとんど消えてしまう可能性があります。
心理音響メトリック: 前述のように、Puszynskiの研究では、シャープネス(知覚される高周波コンテンツに関連)、およびラフネス(振幅または不協和音の変動)などのメトリックをチェックし、有意な木材効果は見られませんでした。特定のラウドネス(臨界帯域内のラウドネス)も、木材によって大きく変化しませんでした。これらの結果は、広範な心理音響の観点から見ると、トーンは木材に関係なく同じ範囲内にとどまったことを意味します。つまり、ギターは、これらの標準的な測定で評価した場合、ボディ材のみが原因で「明るい」から「暗い」または「滑らか」から「ハーシュ」に変化することはありません。変化する可能性のあるものは、より微妙です。エンベロープ形状(サウンドが時間とともにどのように進化するか)といくつかの細かいスペクトルの詳細です。耳は非常に遅い振幅の変化には比較的鈍感であるため、カットオフポイントを注意深く聞いていない限り、減衰テールの違いは気づかれない可能性があります。一方、音のアタック部分は、より知覚的に重要です(楽器の音は主に最初の数ミリ秒から識別します)。木材がアタックトランジェントに影響を与える場合(例えば、硬い木材は、よりスナッピーでパーカッシブなアタックを生み出す可能性があります)、サスティーンの違いがなくても、それは可聴になる可能性があります。一部のギタリストは、非常に硬いボディ(アクリルまたは金属ボディなど)を備えたギターは、木製のギターよりもシャープなアタックとフルボリュームへの立ち上がりが速いと逸話的に報告しています。これは、プラックの最初の瞬間における減衰が少ないことに関連している可能性があります。アタックトランジェントに関する厳密な研究はまれですが、心理音響分析にとって有望な分野です。
ブラインドテストとリスナーバイアス: ギターコミュニティの間で非公式な「ブラインドテスト」が行われており、リスナーはトーンウッドでギターを区別しようとします。その結果はさまざまであり、ブランド、ピックアップ、その他の要因が一定の場合、多くのリスナーは耳だけでトーンウッドを確実に区別できません。これは、期待バイアスが役割を果たしていることを示唆しています。ギターが貴重な木材で作られていることを知っている場合、より豊かなトーンを期待する可能性があり、したがって、それを聞いていると報告する可能性があります。真に検出率を定量化するには、適切な二重盲検テスト(エレキギターで公に存在するものはほとんどありません)が必要です。Acta AcusticaのPaté 2015指板研究は、数少ない正式なリスニングテストの1つであり、ギタリストによる偶然以上の識別を示しましたが、違いは「夜と昼」ではないとも指摘しました。リスナーは、推測するよりもエボニーとローズウッドを少しよく区別できましたが、100%完全に区別できたわけではありません。これは、効果は現実的ではあるものの、控えめであり、気づくには集中力が必要であることを示しています。
人間の聴覚閾値: もう1つの側面は、聴覚の周波数依存性です。耳は2〜5 kHzの周波数で最も敏感であり、非常に低い周波数ではそれほど敏感ではありません。木材の変化が主に100 Hz(低いEの基本周波数)または6 kHzの微妙な倍音に影響を与える場合、それらは聴覚感度の端に近い可能性があります。ただし、3 kHzでのわずかな変化は、より顕著になります。ギターの最も強い弦の基本周波数(開放弦)は、〜80 Hzから330 Hzの間にあり、耳の感度が低く、室内の音響が支配的になる可能性があります。Rayらが発見した違いは、主に高調波(例えば、300〜600 Hzの範囲)にありました。これは、おそらくいくらか可聴です。一方、Jasińskiのスペクトルの違いには、おそらく高周波倍音(1〜4 kHz)の変化が含まれており、リスナーが聞き分けることができた理由です。
要約すると、音響心理学的に、ソリッドエレキギターにおけるトーンウッドの違いは、微妙さの閾値にあります。隔離された状態では聞こえる(そして、最小可聴差を超えることが測定されている)ことがありますが、通常の使用では、他の要因によって容易に覆い隠される可能性があります。熟練した耳であれば、あるギターと別のギターで、わずかに速い減衰や、より多くの高音域の「空気感」を検出できるかもしれませんが、平均的なリスナーは、指摘されない限り決して気づかないかもしれません。
神話 vs. 科学的発見
ギターの世界には、トーンウッドに関する多くの主張があります。ここでは、一般的な神話と、厳密な科学が示すものとを対比させます。
-
神話:「エレキギターでは木材はまったく重要ではなく、すべてエレクトロニクスだ。」
発見:厳密な意味では誤りです。木材は確かに影響を与えますが、その影響はアコースティックギターよりもはるかに小さいです。科学的な研究では、木材の選択が弦の振動を調整することで、サステインと音色の微妙な側面に影響を与えることが示されています。ピックアップとエレクトロニクスが全体的な周波数特性を支配しますが、木材による違いは、大きくはないものの、適切な条件下では測定可能で、聴覚でも認識できます。「すべてエレクトロニクス」というわけではなく、むしろ木材は弦との複雑なフィードバックシステムの一部を形成しています。ただし、実際的な観点からすると、ピックアップを交換する方が、ボディの木材を交換するよりも、音色に明らかな変化をもたらします。科学は、木材の効果を微妙な周波数特性の調整とサステインの変化として定量化することで、この見方を支持しています。つまり、音色を大きく変化させるわけではありません。 -
神話:「重いギターほどサステインが長い。」
発見:ある程度までは、多くの場合当てはまります。重いギターは通常、木材の質量が多く(そして多くの場合、より硬い木材)、弦の固定点での機械的インピーダンスが増加し、弦からのエネルギー損失が少なくなります。実験では、高密度で剛性の高い木材(アッシュやメイプルなど)で作られたギターは、軽量で柔らかい木材よりも、わずかに長いサステインを持つ傾向があることが確認されています。Rayらの研究では、振動減衰を低減し、サステインを向上させるために、「より秩序だった構造を持つ、より重い木材」を明確に推奨しています。ただし、重量だけが唯一の要因ではなく(構造や木材の内部減衰も重要です)、ある程度を超えると、極端に重い材料(金属製のボディなど)は、他の損失メカニズムのために、比例したサステインの利点をもたらさない可能性があります。しかし、経験則として、この民間伝承には根拠があります。例えば、クラシックな重いレスポール(マホガニー+メイプル)はサステインで知られていますが、非常に軽いギターは、より「オープン」な共鳴を持つかもしれませんが、自然なサステインは短くなります。 -
神話:「特定の木材は固有の音色の「色」を持っている(例:マホガニー=暖かい、メイプル=明るい)。」
発見:部分的には真実ですが、誇張されています。アコースティック楽器では、これらの木材の音色の説明にはメリットがあります。ソリッドエレキギターでは、音色の色の違いは微妙です。マホガニーは一般的に、メイプルよりも剛性が低く、減衰が大きいため、高周波振動のサステインがわずかに減少する可能性があります。したがって、一般的に主張されているように、「暖かい」(つまり、明るくない)音色になります。メイプルの高い剛性は、より多くの高周波振動を保持し、潜在的に「明るい」アタックを生み出す可能性があります。スペクトルの違いに関する科学的な測定は、これらの固定観念とある程度一致しています。硬い木材は、より多くの高周波エネルギーをサポートする傾向があり(したがって、より明るいサウンド)、減衰の高い木材は、高調波をより速く減衰させることができます(したがって、より暗いサウンド)。ただし、これらの効果の大きさは小さいです。トーンノブを回して音色を変えるほど、EQプロファイルが大きく変わることはありません。したがって、木材Xはエレキギターにおいて木材Yよりもわずかに明るい傾向があると言うことはできますが、ブラインドテストでは、多くの人がそれを確実に聞き分けるのに苦労します。誤りがあるのは、その大きさに関する神話です。一部のマーケティング用語は、それぞれの木材種が劇的にユニークな音色を持っていると信じ込ませようとしますが、それは管理された証拠によって裏付けられていません。違いは現実のものですが、わずかです。 -
神話:「最高のエレキギターのサウンドには、エキゾチックな熱帯産のトーンウッドが必要だ。」
発見:証拠によって裏付けられていません。多くのエキゾチックな木材(ローズウッド、エボニーなど)は、エレキギターにおける科学的に証明された音色の優位性よりも、美観、耐久性、または歴史的な名声のために使用されています。持続可能性への懸念が高まる中、研究者たちは、エレキギター用の地域産の、または非伝統的な木材を調査しています。Jasińskiらの聴覚性に関する研究は、熱帯産のトーンウッドの使用に疑問を投げかけることが動機の一部であり、代替品がそれらの熱帯産の木材の知覚可能な範囲内でサウンドを生成できることを発見しました。言い換えれば、木材が同等の機械的特性(剛性、密度、減衰)を持っていれば、非常に類似した結果を生み出すことができます。木材の選択は、神秘性ではなく、材料特性(弾性率など)によって導かれるべきです。実際、Puszynskiの論文は、弾性率が樹種名よりもサステインとピーク出力と相関することを示唆しています。これは、剛性の高い国産木材が、より希少なエキゾチックな樹種と同じように機能する可能性があることを意味します。特定された希少な木材のみがエレキギターで「プレミアムトーン」を生み出すという神話は、主にマーケティングによるものです。製造業者と科学者は、同じハードウェアと設計を使用した場合、オーク、パイン、チェリー、その他の非伝統的な木材から作られた優れた楽器が、通常の木材と同等の音響性能を持つことを示しています。 -
神話:「ボルトオンネックのギターは、木材の結合が弱いため、セットネックのギターよりもサステインが短い。」
発見:木材の種類というよりは、構造に関連して、ある程度の真実があります。ボルトオンネック(フェンダースタイルなど)は、エネルギー損失のポイントとなる機械的な接合部を導入しますが、接着されたセットネック(ギブソンスタイル)は、より連続的な木材の接続を提供する可能性があります。フレッシャーのデッドスポットに関する研究には、ボルトオンギターとセットネックギターの比較が含まれており、サステイン特性と共鳴挙動の違いが観察されました。ただし、その違いは単に「サステインが多いか少ないか」ではなく、共鳴がどこにあるかに影響を与える可能性があります(したがって、どの音がデッドスポットになるか)。適切に実行されたボルトオンは、依然として非常に優れたサステインを持つことができます(そして、サステインで知られる多くのベースギターで使用されています)。この神話は、接合部の設計、ネックの質量、および木材の接触面積の複雑な相互作用を単純化しすぎています。木材の観点からすると、組み立て方法と構造的な結合(ネジ、接着剤など)も、弦からエネルギーがどのように流出するかを支配することを思い出させます。同じ木材で作られたが、ネックジョイントが異なる2本のギターは、同じ設計で作られたが、木材の種類が異なる2本のギターよりも、おそらく違いが大きくなります。したがって、この記事の焦点ではありませんが、木材片がどのように接続されているかが、楽器の振動挙動にとって木材自体と同じくらい重要であることに注意する価値があります。 -
神話:「磁気ピックアップは弦の振動のみを拾うため、木材が行うことはすべて無意味だ。」
発見:この神話は、木材の役割を誤解していることから生じます。ピックアップが感知するのは、木材の動きではなく、弦の動きであることは事実です。しかし、木材は弦が何をしているかに影響を与えます!木材が弦のエネルギー損失を速めたり、その動きを変化させたりすると、ピックアップの出力はそれを反映します。実験では、ピックアップ信号が木材によって引き起こされる効果(異なる減衰時間や周波数など)の痕跡を運ぶことを明確に示しています。ピックアップは、弦が特定の振動をしている理由を「気にしません」。各瞬間の機械的な動きを電気信号に変換するだけです。したがって、柔らかい木材が特定の高調波を20%速く減衰させる場合、ピックアップはその減衰を忠実に再現します。この神話は、木材が空気を振動させることによって音を作り出すアコースティックギターとの混同から生じている可能性があります。エレキギターでは、木材は新しい音を直接追加しませんが、弦の挙動を調整し、それがピックアップの出力を調整します。したがって、ピックアップが木材を無関係にすると言うのは誤りです。より正確な表現は、「ピックアップとエレクトロニクスは木材の効果を覆い隠す可能性がありますが、排除はしません。」となります。
結論:物理学と知覚の調和
ソリッドボディのエレキギターは、振動する弦とそれを支える木製の構造の結婚です。そして、電磁ピックアップがサウンドを変換しますが、木材はバックグラウンドで静かに弦の振動を形作ります。厳格な学術研究により、ボディ、ネック、または指板の木材の選択が、サステイン時間、周波数特性、および測定可能な方法でデッドスポットの発生に影響を与える可能性があることが示されています。一般に、密度が高く、剛性の高い木材は、エネルギー損失を最小限に抑えることで、より長いサステインとわずかに明るい音色を提供し、軽量またはより減衰された木材は、サステインを短くし、特定の周波数を柔らかくする可能性があります。これらの効果は振動力学に根ざしています。材料の剛性、質量、および内部減衰の違いは、弦のエネルギーが吸収または反射される方法の違いにつながります。
ただし、大きさも重要です。科学文献からのコンセンサスは、エレキギターにおけるトーンウッドの効果は二次的な影響であるということです。それらは存在しますが、ピックアップ、アンプのEQ、またはギターの構造設計(ブリッジの種類、ネックジョイントなど)などの主要な要因と比較して比較的小さいです。音響心理学的分析とブラインドテストは、リスナーが制御された条件下で木材の違いを識別できる一方で、それらの違いは、特に他のサウンドや歪みが加わると、典型的な聴覚の閾値付近になることが多いことを示しています。演奏者やカジュアルなリスナーにとって、木材によってもたらされるニュアンスは、マスクされるか、単に音楽体験にとって重要ではない可能性があります。
神話の解明という観点から、多くの単純化された主張は精査に耐えられません。木材だけでは、エレキギターのサウンドが突然完全に異なる楽器のように聞こえることはありません。エレキギターのサウンドチェーンの根本的な制限を回避する魔法の「トーンウッド」はありません。同時に、木材がゼロの影響を与えるという全面的な否定は不正確です。より正しい見方は、木材にはある程度の影響があるということですが、それを確実に検出するには、高解像度の測定または注意深いリスニングを使用する必要があります。このニュアンスのある立場は、実際には多くのギタリストの経験に反映されています。彼らは、異なる木材のギター間のフィーリングや音色の微妙な違いを説明するかもしれませんが、それらの違いは小さく、アンプやエフェクトの選択によってしばしば上書きされることも認めています。
実際的な意味:音色の洗練の最後の1オンスを求めるギター製作者や愛好家にとって、これらの発見を理解することは役立ちます。最大のサステインが目標である場合は、剛性が高く、減衰の少ない木材(およびジョイントでのエネルギー損失を最小限に抑える設計)を使用すると有利になります。特定の音色のバランスが必要な場合は、木材を微調整ツールの1つとして使用できます。たとえば、わずかにスナップを効かせるためにメイプルネックまたはエボニー指板を選択したり、高周波の減衰の微妙な変化を知って、暖かさを加えるためにマホガニーを選択したりします。一方、安価な木材や複合材料が音色を台無しにするのではないかと心配している人にとって、材料が適切な構造特性を備えている限り、結果として得られるサウンドは、耳で従来のトーンウッドと事実上区別できなくなる可能性があるという安心感を提供します。持続可能性の観点はここで重要です。エキゾチックなトーンウッドが不足していることを考えると、Jasińskiの研究のようなものは、樹種名ではなく、機械的特性のマッチングに焦点を当てることで、音響的な犠牲を払うことなく代替木材を使用できることを示唆しています。
継続的な研究:ギター音響の分野は発展し続けています。新しい方法(レーザー振動分析、高度な信号処理、厳密な二重盲検リスニングテストなど)が、すべてのコンポーネントの影響をさらに解明するために適用されています。将来の研究では、仕上げ(ラッカーの厚さ)、木材の経年変化、または音色に対するネック補強(トラスロッド、カーボンファイバー)の役割など、他の要因を調査する可能性があります。今のところ、厳格な研究によって裏付けられているように、エレキギターにおけるトーンウッドに関する真実は、次のように要約できます。トーンウッドは、ソリッドボディギターのサウンドを繊細な方法で形作ります。それらは、振動結合と減衰に影響を与え、それがサステインと微妙な音色に影響を与えます。これらの効果は現実的で測定可能ですが、通常は小さいです。精査すれば聞こえますが、多くの場合、信号チェーンのより大きな要素によって覆い隠されます。これを知っていれば、プレイヤーと製作者は、神秘的な畏敬の念や皮肉な拒絶ではなく、木材がエレキギターの音色の式にどのように適合するかについてのバランスの取れた、証拠に基づいた理解を持って、このトピックにアプローチできます。
参考文献
学術論文
-
Ahmed, Sheikh Ali, & Adamopoulos, Stergios. (2018). さまざまな湿潤条件下での改質木材の音響特性と、楽器との関連性。応用音響学、140、92–99。 https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2018.05.017
-
Ahvenainen, Patrik. (2019). エレキギターで使用される木材の解剖学的構造と機械的特性。IAWAジャーナル、40(1)、106–S6。 https://doi.org/10.1163/22941932-40190218
-
Bennett, B. C. (2016). 木の音:ギターやその他の弦楽器における木材の選択。経済植物学、70(1)、49–63。 https://doi.org/10.1007/s12231-016-9336-0
-
Calvano, Silvana; Negro, Francesco; Ruffinatto, Flavio; Zanuttini-Frank, Daniel; & Zanuttini, Roberto. (2023). アコースティックギターにおける木材の使用と持続可能性:グローバル市場に基づく概要。Heliyon、9(4)、e15218。 https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15218
-
Carcagno, Samuele; Bucknall, Roger; Woodhouse, Jim; Fritz, Claudia; & Plack, Christopher J. (2018). スティール弦アコースティックギターの知覚される品質に対する裏板の木材の選択の影響。アメリカ音響学会誌、144(6)、3533–3547。 https://doi.org/10.1121/1.5084735
-
Jasiński, Jan; Oleś, Stanisław; Tokarczyk, Daniel; & Pluta, Marek. (2021). エレキギターのトーンウッドの可聴性について。音響学アーカイブ、46(4)、571–578。 https://doi.org/10.24425/aoa.2021.138150
-
Martinez-Reyes, José. (2015). マホガニーの絡み合い:メキシコ、フィジー、およびギブソンレスポール間の環境物質性。マテリアルカルチャージャーナル、20(3)、313–329。 https://doi.org/10.1177/1359183515594644
-
Paté, Arthur; Le Carrou, Jean-Loïc; & Fabre, Benoît. (2015). 工業用エレキギター製造におけるモーダルパラメータの変動性:製造プロセス、木材の変動性、およびルシアーの決定。応用音響学、96、118–131。 https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2015.03.023
-
Paté, Arthur; Le Carrou, Jean-Loïc; Navarret, Benoît; Dubois, Danièle; & Fabre, Benoît. (2015). ギタリストの知覚に対するエレキギターの指板材の影響。Acta Acustica united with Acustica, 101(2), 347–359. https://doi.org/10.3813/AAA.918831
-
Paté, Arthur; Le Carrou, Jean-Loïc; Teissier, François; & Fabre, Benoît. (2015). 製造工程における、公称上同一のエレキギターのモーダル挙動の進化。Acta Acustica united with Acustica, 101(3), 567–580. https://doi.org/10.3813/AAA.918853
-
Puszyński, Jakub; Moliński, Wojciech; & Preis, Andrzej. (2015). エレキ弦楽器の音質に対する木材の影響。Acta Physica Polonica A, 127(1), 114–116. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.127.114
-
Zorič, Anton; Kaljun, Jasmin; Žveplan, Ervin; & Straže, Aleš. (2019). エレキギターのソリッドボディのための音響特性に基づいた木材の選定。Archives of Acoustics, 44(1), 51–58. https://doi.org/10.24425/aoa.2019.126351
論文および学位論文
-
Applegate, Brian Charles. (2021). 象徴的なギターのトーンウッドの隆盛と衰退、および代替種の評価。エディンバラ大学博士論文。http://dx.doi.org/10.7488/era/1695
会議議事録
-
Paté, Arthur; Le Carrou, Jean-Loïc; & Fabre, Benoît. (2013). 黒檀 vs. ローズウッド:ソリッドボディのエレキギターのサウンドに対する指板の影響に関する実験的調査。Proceedings of the Stockholm Musical Acoustics Conference (SMAC 2013) (pp. 182–187)に掲載。ストックホルム、スウェーデン。
-
Margetts, Rebecca, & James, Michael. (2023). ギターのトーンウッドの特性の定量化。Proceedings of the 154th Audio Engineering Society Convention (Paper 76)に掲載。エスポー、フィンランド:Audio Engineering Society。ISBN 978-1-942220-41-1。
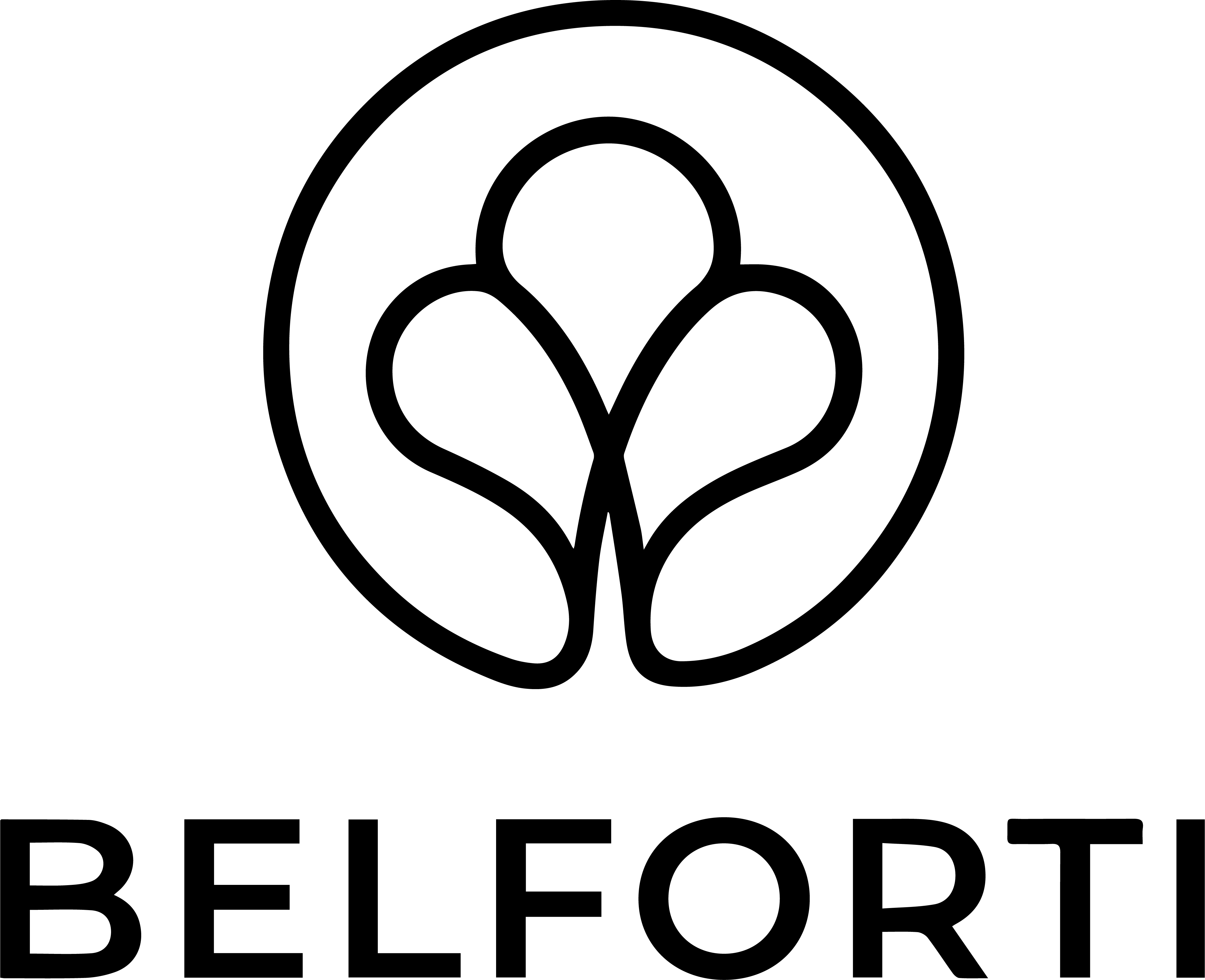
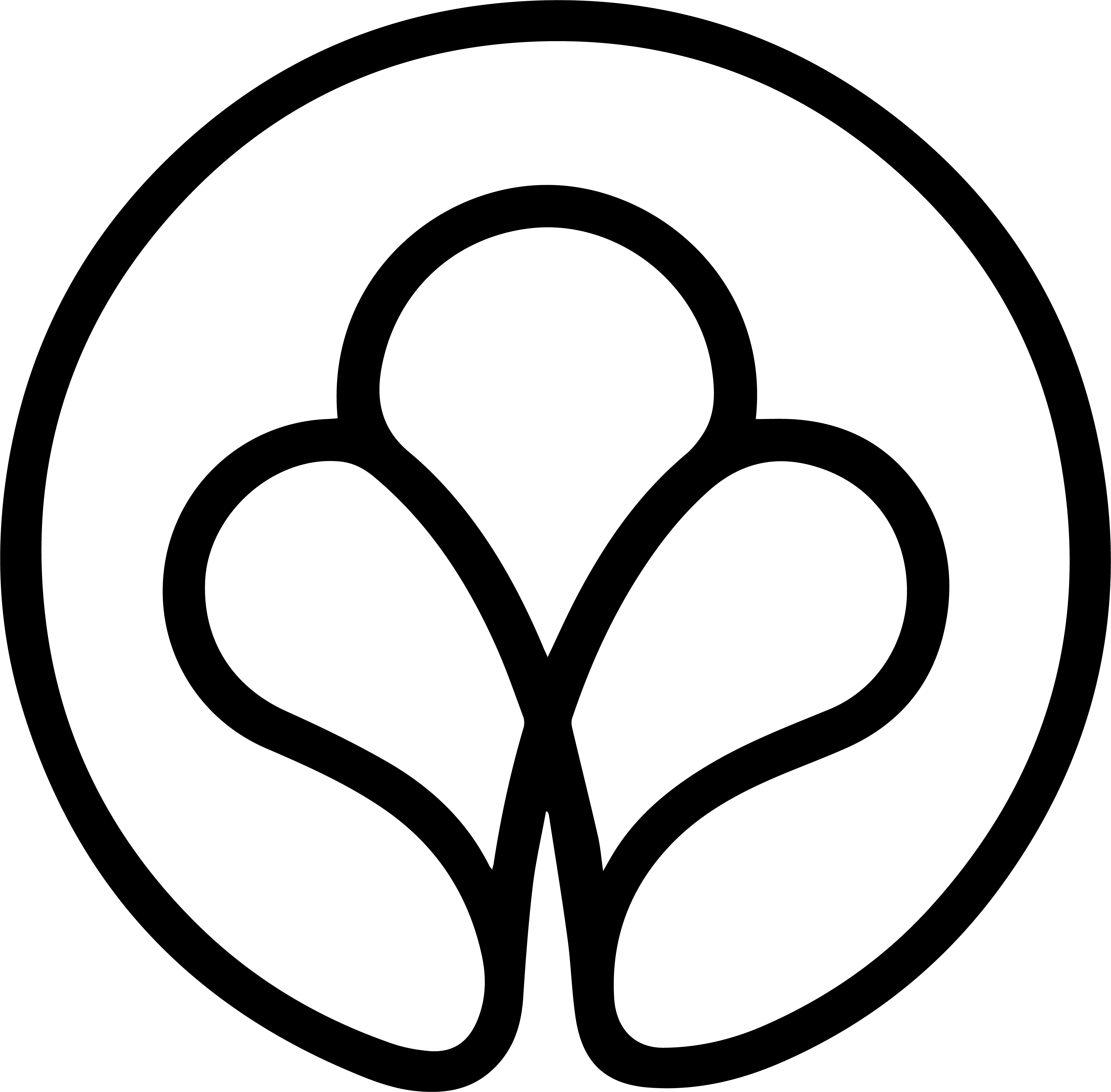



シェア:
パリの弦楽器製作者 – 光の都における伝統、技術、そして革新