金継ぎは、15世紀頃に現れたとされる日本の伝統的な修復技術です。日本の職人が何世紀にもわたって習得してきた漆芸の一部であり、主に陶磁器の修復に使用されることで有名です。
その主な目的は、壊れた陶磁器を修復したり、木製品の自然な不完全さを強調したりすることです。ほとんどの修復技術が損傷箇所を完全に隠すことを目的としているのに対し、金継ぎの哲学は、損傷した物の欠点を隠すのではなく、受け入れることです。それは、物の過去、その歴史、そしてそれが経験したであろうあらゆる事故を考慮に入れます。
陶器の破損は、もはやその終わりや廃棄を意味するのではなく、新たな始まり、別のサイクルの始まり、そしてその使用の継続を意味します。したがって、修理を隠すのではなく、それを強調することが重要です。

金継ぎは、私たちが人生にどのように向き合うべきか、そして私たちの経験や苦難が私たちをより強く、より美しくすることができるという考え方の比喩としてよく見られます。金継ぎは、私たちの欠点を覆い隠したり、無視したりするのではなく、変化と改善の触媒として歓迎することを教えてくれます。
金継ぎのプロセスでは、壊れた陶器の破片を、日本の固有種であるウルシの木から抽出された漆と呼ばれる特殊な漆と、選択した貴金属を使用して注意深く修復します。修復されたアイテムは研磨され、仕上げられ、その過去の歴史と個性が吹き込まれた唯一無二のアイテムになります。
近年、金継ぎは、さまざまな状況における修復および修復方法として、また、物の欠点と個性を評価する方法として、より広く知られるようになりました。壊れた花瓶や木製家具の修理に使用されるかどうかにかかわらず、金継ぎは、人生のひび割れや不完全さの中に見出すことができる回復力と美しさを力強く思い出させてくれます。
Belforti Instrumentsでは、長年にわたる日本の繊細な芸術への憧憬を主な理由として、さまざまな理由から金継ぎを使用し始めました。私たちの金継ぎの使い方は、本来の意図とは少し異なっており、おそらく巨匠たちにはそのように認識されないであろうことを深く認識しています。しかし、私たちはこの方法で修理するために、貴重なトーンウッドを意図的に壊したり、ひびを入れたりするつもりはありませんよね?

私たちは、漆から金属粉、女性用のヘアブラシ(このプロセスで女性が傷つけられることはありませんでした)まで、すべてのオリジナルの調達された素材を使用しながら、主にその装飾的な側面のためにこの方法を使用しています。私たちは可能な限り元のコンセプトに忠実であり続けようと努めていますが、ギター製作の制約に合わせて少しひねりを加えています。
もしあなたが何か違う、そしてあなたのカスタムギターのためにユニークなものを夢見ているなら、私たちのカスタマイズオプションをチェックするか、私たちの優れた仕上げのいずれかであなたの新しいBelfortiを注文してください!
そして、この芸術の形を自分自身で体験したいフランス国民の皆様には、Nicolas Pinonに連絡を取ることを強くお勧めします。彼は初心者や修理の専門家のために素晴らしい入門コースを提供しています!
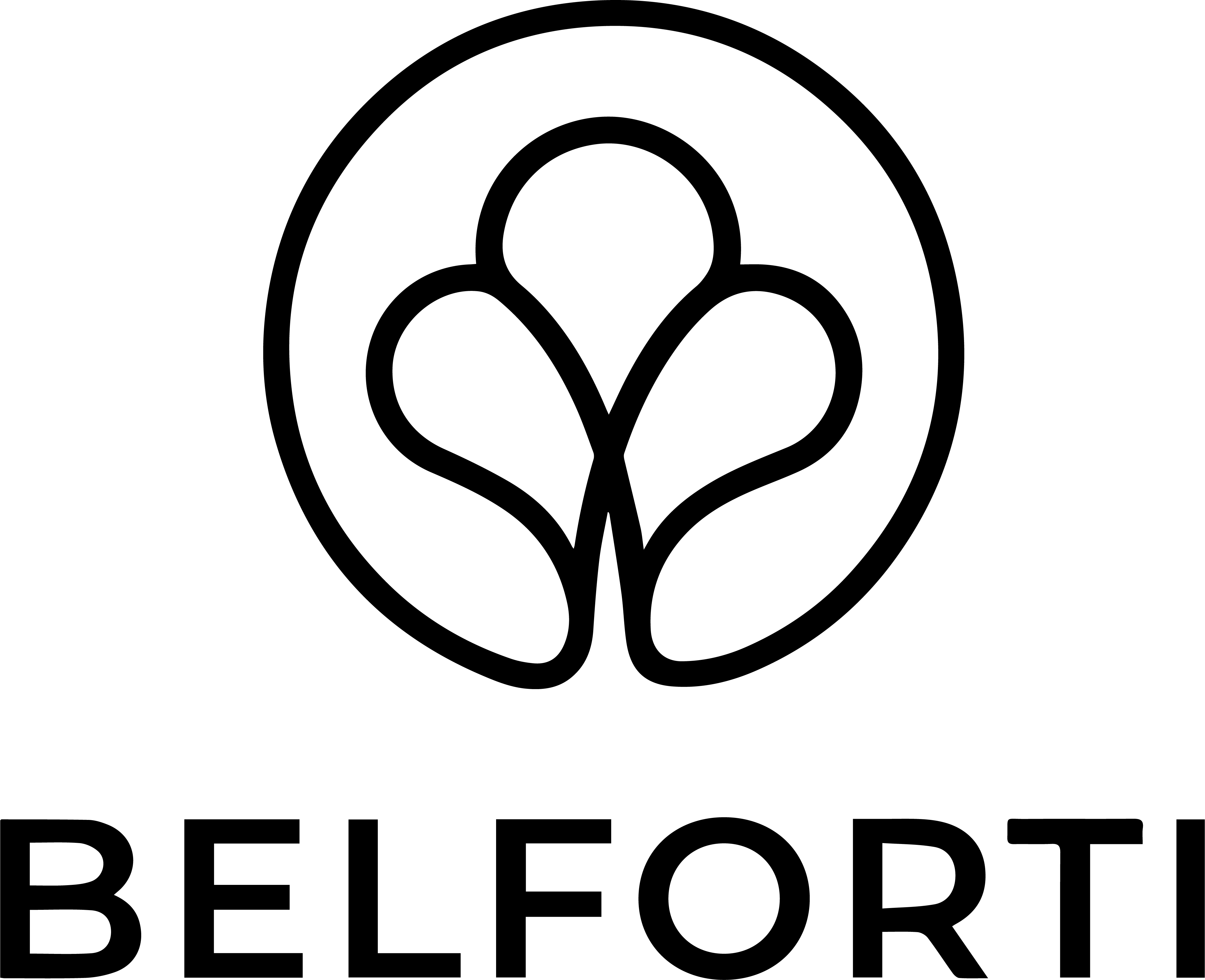
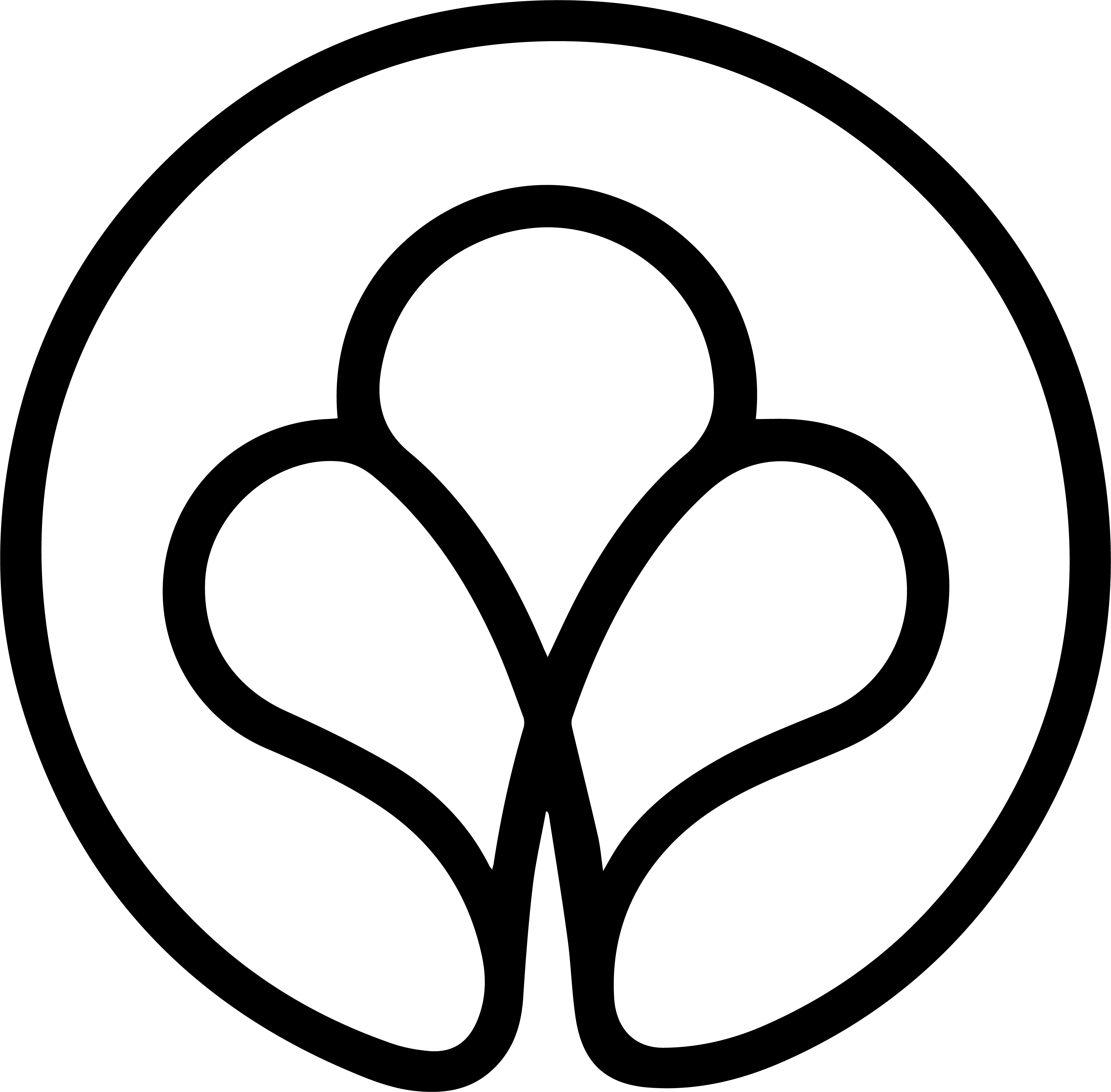



シェア:
ギターのお手入れ方法